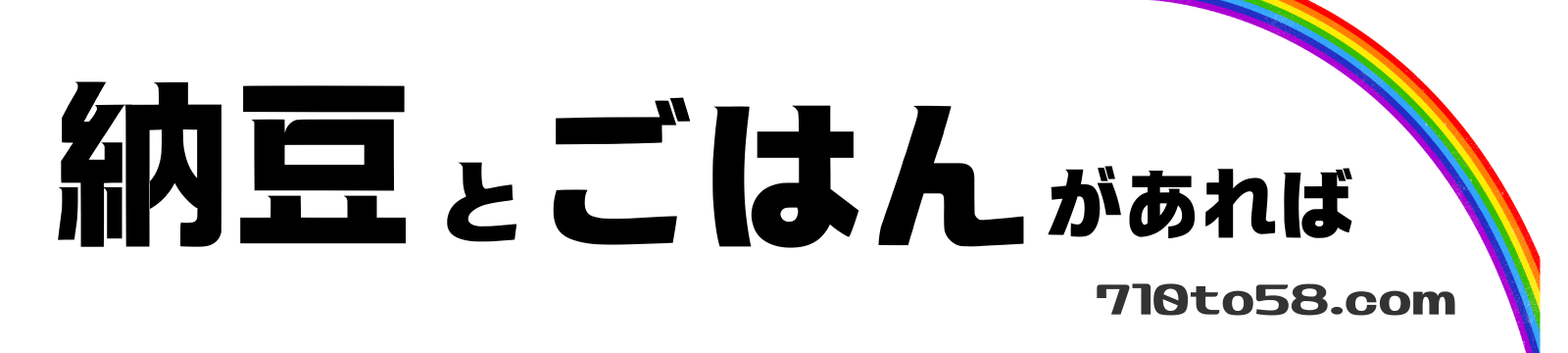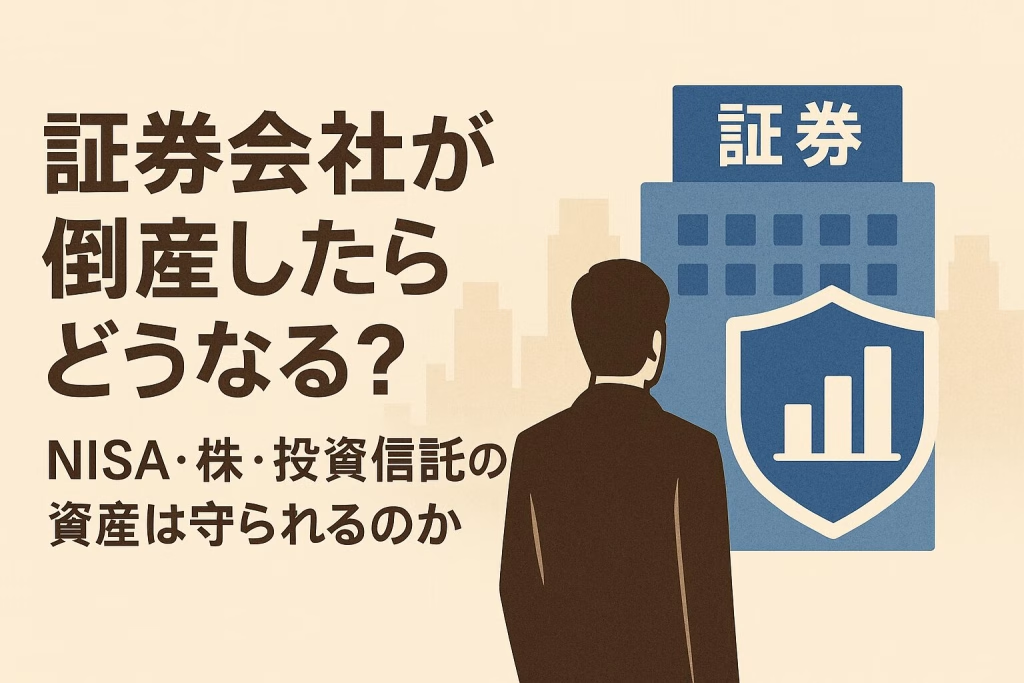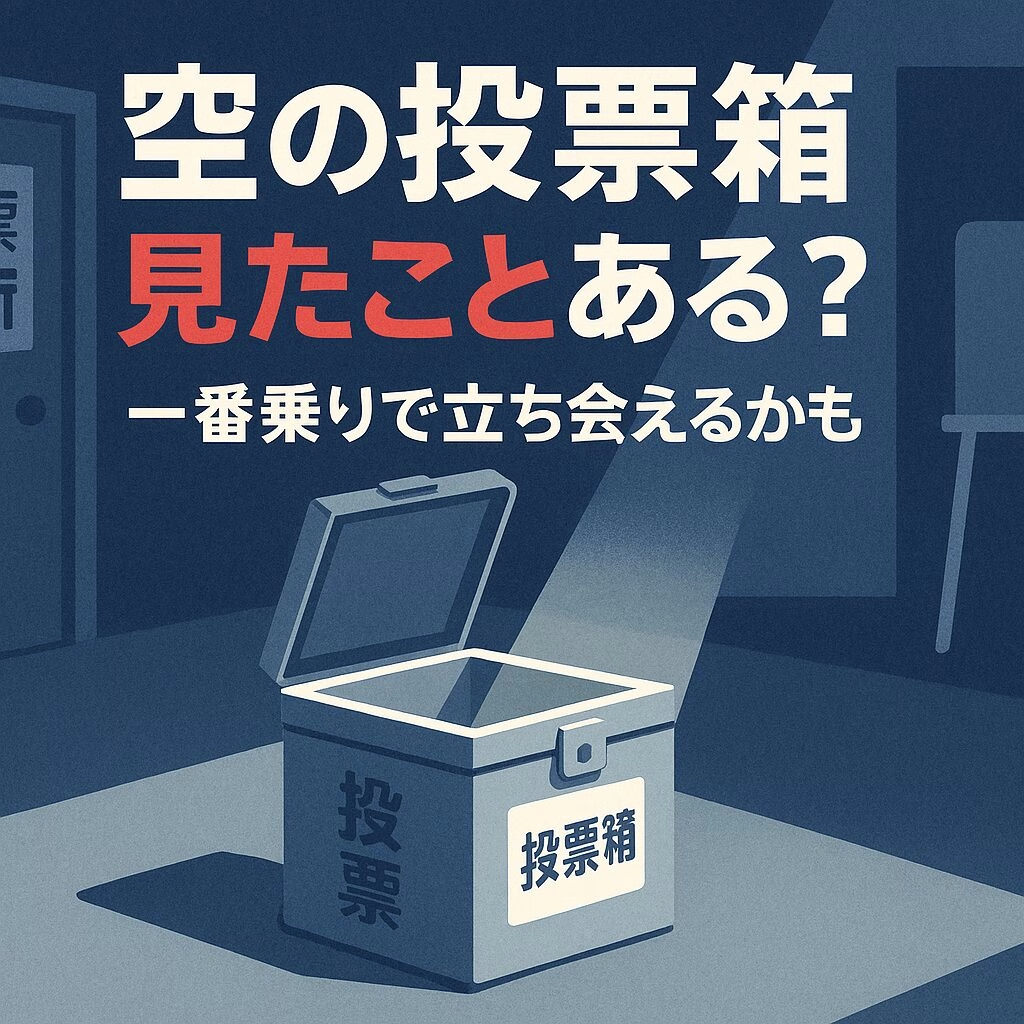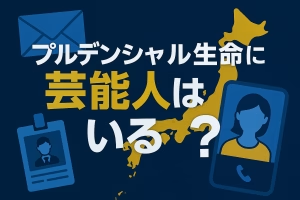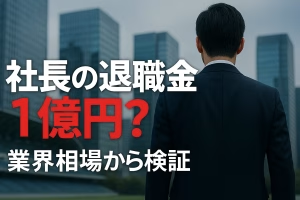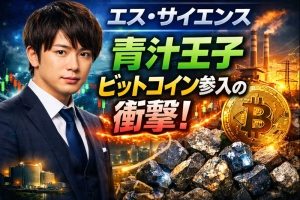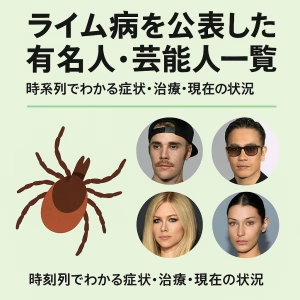今、なぜ「アニマルセラピー」が注目されているのか?

検索が急増中「ペット セラピー」関連ワード
近年、「ペットセラピー」「アニマルセラピー」「犬 猫 癒し」「動物と健康」といったキーワードがWeb検索で大きく伸びています。
2023年には全国の医療・福祉施設でアニマルセラピー導入数が前年に比べ約1.7倍増加。
心身両面の健康を求めて「動物と過ごしたい」「ペットとふれあいたい」と感じる人が急増しています。
動物と人間の絆がもたらす医療的価値
高齢化社会やコロナ禍など、多様な社会変化の中で「孤独」「ストレス」「心の疲れ」を抱える人が増加。
そんな今、人間と動物の絆が心の健康・生きる力をサポートするという科学的な価値が見直されています。
犬や猫と過ごすことで「抑うつ感や不安が20%低減」「入院患者の笑顔や発語数が倍増」したという医療現場の報告もあります。
アニマルセラピーとは?基本の定義と仕組みを解説

アニマルセラピーとペットセラピーの違い
「アニマルセラピー」は、動物を介して心や身体に癒しや健康促進をもたらす専門的な活動全般を指します。
- 動物介在療法(AAT)
- 医師などの専門家が治療補助として実施
- 動物介在活動(AAA)
- 主に介護・福祉施設や学校で、ふれあいによるQOL向上
- 動物介在教育(AAE)
- 教育現場で命の大切さや感情教育を行う
一方「ペットセラピー」は、より気軽な家庭での動物とのふれあいを指すことも多い言葉です。
導入されている施設と実施方法
- 医療現場
- 入院患者へのリハビリや精神ケア
- 高齢者施設
- 認知症ケアや孤独感緩和、会話のきっかけ作り
- 特別支援学校・教育現場
- 子どもの情緒安定や社会性向上
- 災害被災地
- 避難所や仮設住宅でのストレスケア
- 活動は専任ボランティアと動物がペアで訪問し、数十分〜1時間のふれあい・会話・簡単な運動等を実施します。
科学が証明!動物がもたらす癒しと健康効果とは

ストレス軽減|オキシトシンと幸福感の関係
犬や猫とふれあうと、愛情ホルモンとも呼ばれる「オキシトシン」や「ドーパミン」の分泌量が増加。
「ふれあい10分でストレス値が12%低下」「心拍数や血圧の安定」が実証されています。
特に猫の“ゴロゴロ音”は心を落ち着かせ、免疫力UP作用も認められています。
うつ・孤独感の緩和データ(高齢者事例)
高齢者施設で半年間セラピー犬を導入した実例では、抑うつ指標・孤独感が平均15〜25%低減し、表情や会話が豊かになったという結果が出ました。
1回10分、週1回のプログラムだけで実感する人が6割を超えています。
犬の散歩と身体活動の関係
犬の飼い主は日常の歩数が平均2700歩増加し、「週2回以上散歩する人」が飼育していない人の約1.3倍。
運動不足・生活習慣病予防にも明確な効果が認められました。

社会性の向上|人間関係にも良い影響
ペットを介すことで「家族間や入居者同士の会話が3倍増えた」「認知症高齢者が自発的に声を出すケースが2倍に」など、
社会性の向上・人間関係の活性化が多数の現場で報告されています。
どんな人・現場で活用されているのか?
高齢者施設での導入事例とその変化
全国の介護施設では2023年度アニマルセラピー導入率が31%。
・笑顔や会話が増え、レクリエーション参加率が30%向上
・認知症高齢者の「徘徊・暴言行動」が20%減った調査も
「パートナーの犬や猫を“孫”のように可愛がる利用者が増え、生きがいになっている」と現場スタッフの声も届きます。

教育現場での感情教育・命の教育
小中学校・特別支援学校では、「命の大切さ」や「他者との共感力」を育むため、セラピー犬・猫とのふれあい活動が積極的に導入。
・発達障がい児の落ち着きUP
・全校の登校率向上(不登校児の年間出席率が15%増加した例も)
教員からは「動物と接すると、普段みられないほど心を開く児童が増えた」といった声が寄せられています。
災害被災地や病院など特別な現場での活用
東日本大震災や令和元年の豪雨被災地では、セラピー動物の「炊き出し&ふれあいプログラム」により、不安感の強い高齢者・子どものストレス軽減やPTSD症状の改善が報告されています。
医療現場では「セラピー動物来訪日だけ食欲が増した」「心臓手術後のリハビリが続けられた」等の感動的な声も。
自宅でできる!初心者向けペットセラピーの始め方
犬・猫・小動物とのふれあいが心に効く
家でペットと過ごす時間も立派な「セラピー体験」。
・休日に犬と散歩
・猫の毛づくろいを観察
・ウサギやハムスターをゆっくり撫でる
これだけで「幸福感UP」「怒りやストレス軽減」といった効果が報告されています。

ペットがいない人でもできる癒し行動とは?
- 近所のペットカフェや動物ふれあいイベントに参加
- 動物園や牧場で温もり体験
- アニマルセラピー動画を見るだけでもリラックス効果あり
高齢者施設でも「訪問セラピー」や「動物ロボット」を活用する現場が増えています。
毎日5分!ストレスケア習慣の作り方
- 朝晩「ペットをなでるだけ5分」から始めてみてください
- 鳴き声に耳を傾ける、呼吸を合わせるといった“マインドフルネス”も推奨
- たとえ短時間でも「継続」がポイント
体験談・実践者の声から見るリアルな効果

高齢者の笑顔・発語が増えた事例
「セラピー犬が来てから、普段は無表情だった母が毎週わらい、犬に“また来てね”と声掛けをするようになりました」(家族談)
高齢者約73%が「気持ちが明るくなった」と回答した調査も。
子どもが落ち着いた、家族の関係が良好に
「犬がいる日は感情が安定し、癇癪が激減。兄弟とも一緒に遊ぶようになった」と母親
家族全体の会話や笑顔、家事協力も増え「家庭の空気が変わった」と喜びの声多数。
犬とのふれあいで日常が変わった一人暮らし男性の声
「ずっと一人が寂しかったが、犬が家に来てから外に出る機会が月6回→20回に。気分転換が増え、仕事の集中力も向上した。」
ペット飼育者は非飼育者より心的ストレス指標が20%低いという確かなデータも裏付けになっています。
注意点|はじめる前に知っておきたいこと
アレルギーや衛生面の注意点
・動物アレルギーや喘息の方は事前に医師に相談
・施設や家庭では手洗い・消毒を徹底し、動物の健康管理も十分に
・特に大人数が触れるイベントでは感染症対策が不可欠です
すべての動物がセラピー向きではない理由
犬や猫にも「社会性」「穏やかさ」「環境適応力」などが必要です。
・攻撃性が強い、過剰に怖がりな動物はストレスや事故リスクが高まります
・人も動物も「安全・安心」であることが大切
セラピー犬・猫のトレーニングや適性とは?

- 専門団体による適性審査・トレーニングあり
- 基本のしつけ(待て・呼び戻し)、どこを触られても嫌がらない
- 他者や多様な環境への適応・穏やかな性格が理想
- 活動前にワクチンや健康診断も必須です
よくあるQ&A
まとめ|動物とのふれあいが心と体を変える
現代人に必要なのは“ふれあいの処方箋”
ストレス・社会的孤立が深刻化する現代社会にこそ、優しいふれあいという処方箋が必要です。
科学も現場も「動物は人の心身を豊かにする力」を裏付けています。

ペットとともに生きる生活がもたらす未来
高齢者から子どもまで、誰もが動物とのふれあいを通して笑顔と前向きな気持ちを手に入れられる時代。
ペットは「単なる癒し」ではなく「人間らしく幸せに生きるパートナー」です。
明日からできる“小さなセラピー体験”を、ぜひ暮らしに取り入れてみてください。癒しは、すぐ隣にいます。
引用・参考
アニマルセラピーの科学的効果や実例は、各種医療団体・福祉現場の調査、栃木医療センター、北部病院、近年の専門記事をもとに執筆しています。