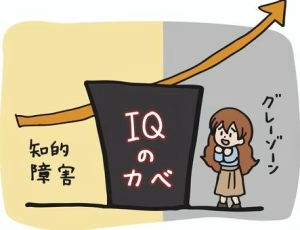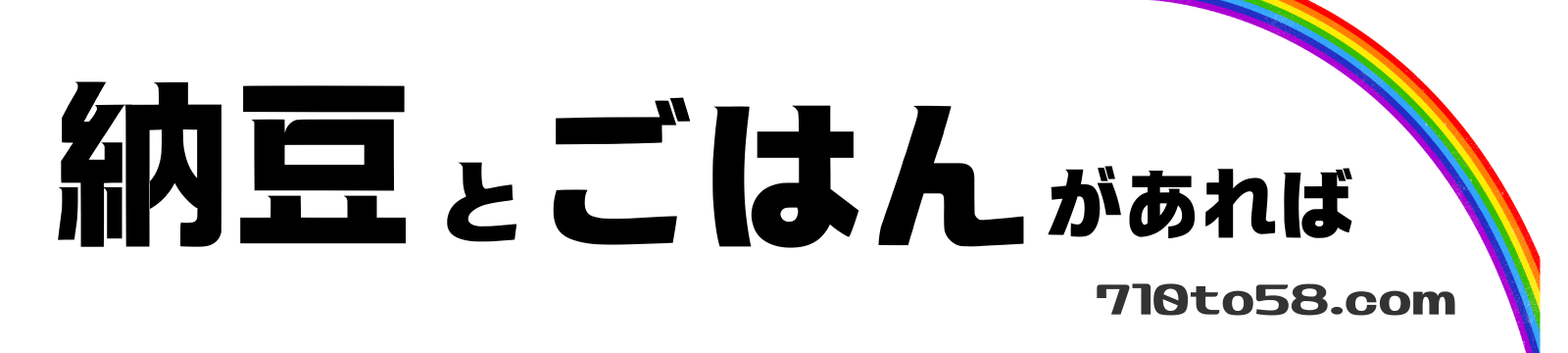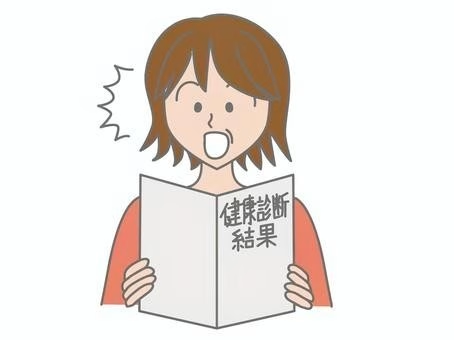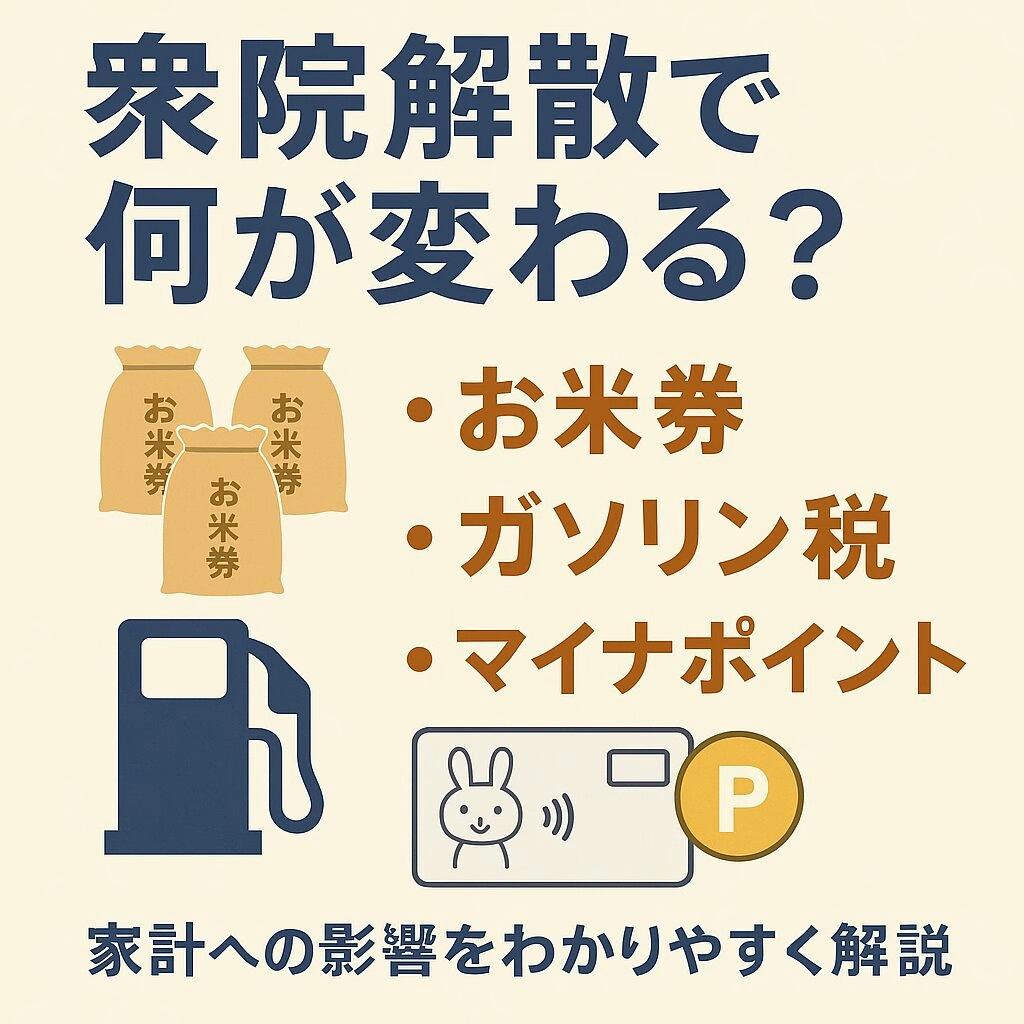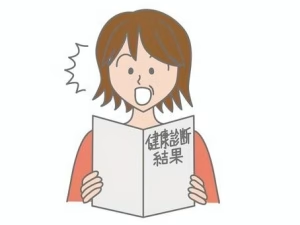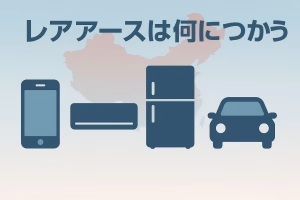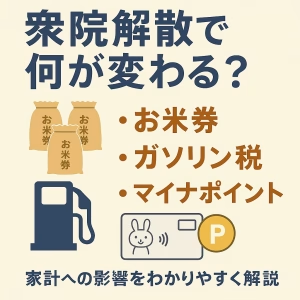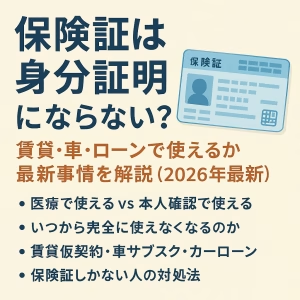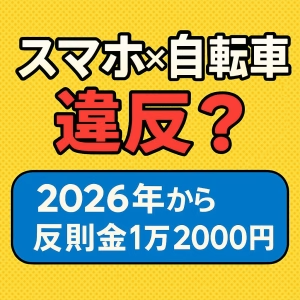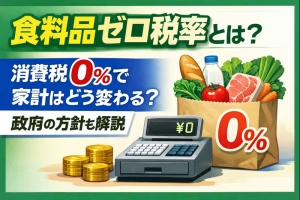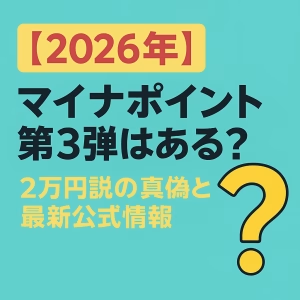小学校入学前に受ける「就学時健康診断(就学時健診)」。
親にとってはわが子の成長を確かめる場である一方、「ひっかかりました」と結果に書かれていると、不安が一気に高まります。
「再検査って不合格の意味?」「もし健康に問題があったら入学できないの?」と悩む保護者も少なくありません。
しかし安心してください。
就学時健診における「ひっかかる」という表現は、合否ではなく「追加で確認が必要」という意味です。
本記事ではその意味や、再検査や経過観察の具体的な流れ、よくある指摘内容について解説していきます。
就学時健診で「ひっかかる」とは?

「ひっかかる」という言い方は少し不安に響きますが、就学時健診には合否判定はありません。
結果通知で示される「要再検査」や「要経過観察」という表現には以下の意味があります。
- 要再検査
- 病院や専門医で再度詳しく調べてください、という医師からの提案。
- 要経過観察
- 今すぐ治療が必要ではないが、成長にともなって変化する可能性があるため定期的に見守りましょう、という意味。
つまり、「ひっかかった = 不合格」「入学できない」という判断ではありません。

あくまで学校生活に支障をきたさないように、早めに医療や支援につなげるための仕組みです。
就学時健診は子どもの成長を守るための「予防的なチェック」。
将来的に大きな困難を避けるため、サポートを整えるための大切な機会なのです。

よくある「ひっかかる」ケース
就学時健診で指摘されやすいのは、次のような内容です。
視力での指摘

- 検査で視力が0.7未満と出た場合、眼科受診を勧められることがあります。
- 遠視や近視、乱視など、就学前に発見できれば早期にメガネで矯正でき、学習に支障をきたさずに済むケースが多数あります。
- 特に「弱視」は早い段階の治療が有効とされるため、就学前に指摘されるのは大切なサインです。
筆者の体験談:視力での指摘を受けたケース
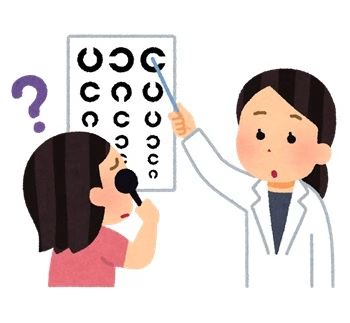
筆者自身も、幼少期から右目の視力が極端に悪く、就学時健診等では毎回「要眼科受診」と指摘されていました。
母親からの遺伝と思われ、眼鏡で矯正を試みましたが、右目を補正するとめまいが出てしまい、現在も右目は未矯正です。
それでも左目と両眼の視力は十分で、裸眼で運転免許も取得できましたし、体育の授業も問題なくこなしていました。
このように「ひっかかる=生活に支障がある」とは限らず、必要な配慮を知ることで安心して学校生活を送ることができます。
聴力での指摘

- 小さな音や片耳の音に反応しにくいとき、耳鼻科での再検査を案内されます。
- 実際には「滲出性中耳炎」など一時的な耳の状態が原因で聴力が落ちていただけ、治療すれば改善する場合も多いです。
- もし聞き取りに課題がある場合でも、学習の遅れではなく「耳の病気のサイン」として捉えられるので、むしろ早期に見つかることがメリット。
筆者の体験談:聴力と中耳炎

筆者の場合、就学時健診では聴力に問題はありませんでしたが、小学校に入ってから中耳炎を発症し、約6か月ほど耳鼻科に通院した経験があります。
幸い完治し、学校生活や体育(水泳など)にも支障はありませんでした。
このように、健診で問題がなくても後から症状が出ることもあり、逆に健診で指摘されても早期に対応すれば問題なく過ごせるケースが多いのです。
歯科での指摘
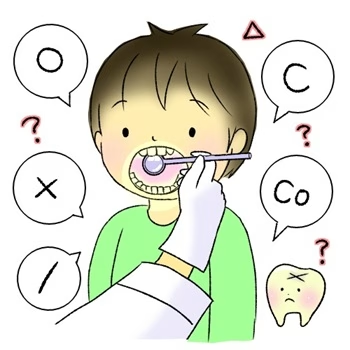
- 虫歯や噛み合わせ、CO(初期虫歯)がよくチェックされます。
- 「再検査=治療が必要」という意味であり、通院のきっかけづくりです。
- 歯並びや噛み合わせの問題は今後の発音や咀嚼にも影響するため、入学前に確認できるのは有益。
筆者の体験談:虫歯になりやすかった子ども時代

筆者自身も小学生のころ、虫歯になりやすい体質で何度も歯科に通っていました。
唾液の分泌量が少ないことが原因と診断され、当時は虫歯のリスクが高かったのですが、現在は歯磨き・歯間ブラシ・3か月ごとの定期健診と歯垢クリーニングを続けることで、10年以上虫歯ゼロを維持しています。
このように、体質的な要因があっても、予防とケアによって健康な状態を保つことが可能です。健診での指摘は、そうした習慣づくりのきっかけにもなります。
発達や知能での指摘

- 言葉がはっきりしない、落ち着きがない、集団での行動が難しいといった点に注目されることがあります。
- この場合「教育相談」や「ことばの教室」など、専門の支援につながる案内が届く場合があります。
- 入学後の大きな困難を防ぐために、事前に学校や教育委員会と情報共有しておくことが目的です。
筆者の体験談:九九が苦手だった子ども時代
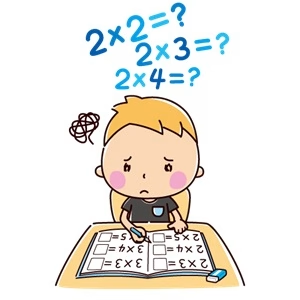
筆者自身も、小学生のころ九九を覚えるのが苦手で、クラスで一番遅れていました。
それでも周囲の支えと自分なりの工夫で学習を続け、最終的には大学まで卒業しています。
大人になってから発達障害の検査を受けたところ、広汎性発達障害と診断されましたが、学生時代は通常の学校生活を送り、友人関係や授業にも大きな支障はありませんでした。
このように、発達の特性があっても、適切な環境と理解があれば、安心して成長していくことができます。健診での指摘は、そうした支援につながる第一歩です。
再検査や経過観察の流れ
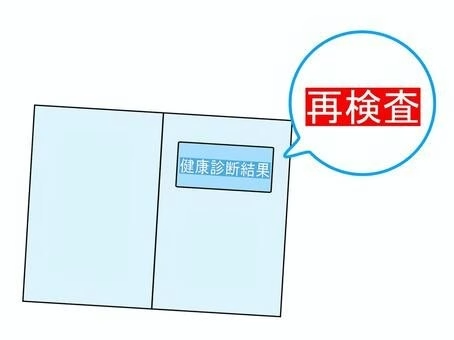
「ひっかかる」結果が出た場合、一般的には以下の流れで進みます。
- 通知・案内を確認
学校や教育委員会から渡される結果通知をしっかりと確認します。
再検査が必要な場合、具体的にどの診療科を受診すればよいか記載されていることが多いです。 - 専門医受診
眼科・耳鼻科・歯科など、必要に応じて医療機関を受診します。
治療や追加検査を受け、必要に応じて「診断書」や「意見書」を学校へ提出する場合があります。 - 教育相談につながるケース
発達や言語などに関わる指摘の場合は、教育委員会が管轄する相談機関につながります。
ここではお子さんの特徴を理解し、入学に向けた支援体制の検討がなされます。 - 経過観察の場合
今後もかかりつけ医で定期的にチェックする程度で良い、というケースもあります。
その場合も「入学不可」を意味するのではなく、「フォローしながら進んでいきましょう」というアドバイスです。
「ひっかかったら入学できない?」の不安に答える

保護者が最も不安に感じるのはここかもしれません。結論を言うと、基本的に「入学できない」ということはありません。
- 日本の就学制度は「原則全員就学」が基本であり、就学時健診に不合格制度は存在しません。
- 健診の目的は「入学できるかどうかを決める」のではなく、「入学に向け必要な支援や配慮を調整しておく」ことです。
- 医療機関の意見を反映しながら、必要に応じて「通級指導教室」や「特別支援学級」などにつながる仕組みもあります。
- 結果的に、子どもが安心して学校生活をスタートできるように整える前向きなプロセスです。
✅ よくある質問(FAQ)
まとめ
- 就学時健診で「ひっかかる」とは「追加の確認が必要」という意味であり、決して合否判定ではありません。
- 視力・聴力・歯科・発達など、よくある指摘は入学後の学校生活に支障を残さないためのチェックです。
- 再検査や教育相談は「入学不可」ではなく「サポート環境を整えるステップ」。
- 不安があれば教育委員会やかかりつけ医に相談することで、安心して入学準備を進められます。
就学時健診での指摘は、子どもにとってより良い環境を整えるための大切なスタートライン。
保護者にとっては不安に感じやすい瞬間ですが、「発見できてよかった」と前向きに受け止め、必要なサポートを受けていきましょう。
👉🔗通知書を確認!就学時健康診断の流れ・持ち物・服装・注意点