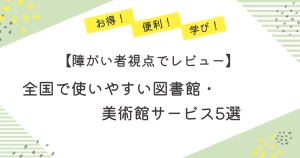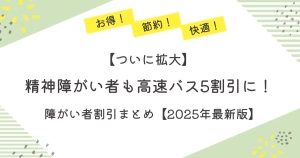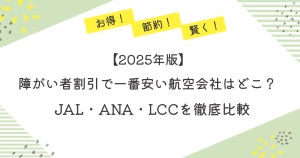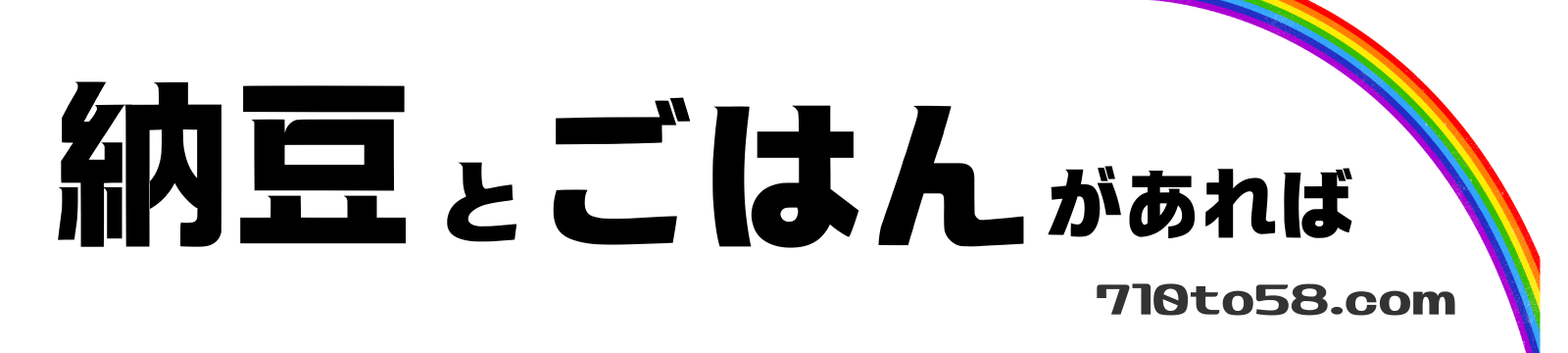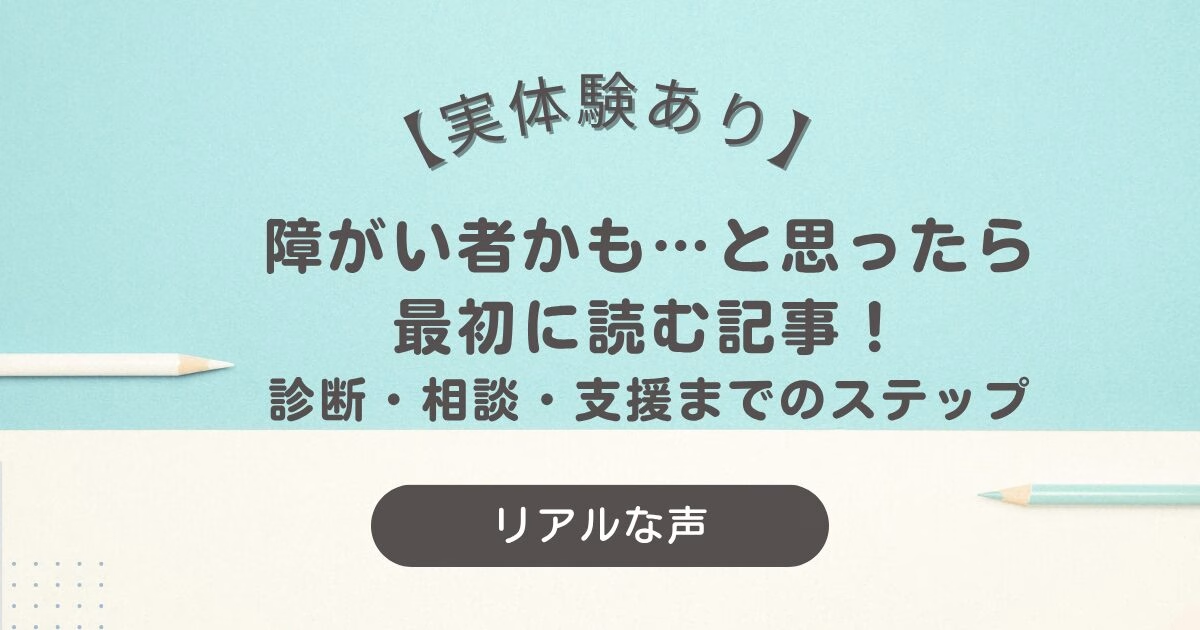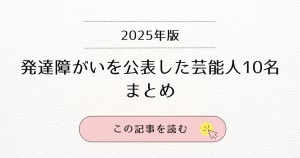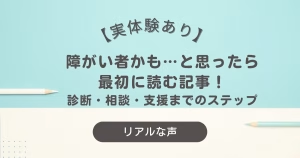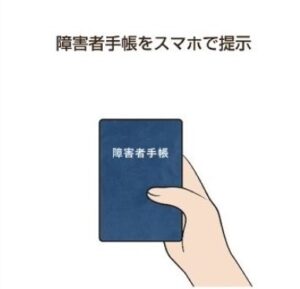「もしかして自分は障がい者かもしれない」「家族や身近な人に気になるサインがある」
――そんな不安や疑問を感じたとき、どこから何を始めればいいのか分からず、悩んでしまう方は多いはずです。
本記事では、発達障がい・精神障がい・知的障がいのサインから相談先、診断や支援の流れまで、初めての方にも分かりやすく丁寧に解説します。
安心して一歩を踏み出せるよう、必要な情報をまとめました。
1. こんなサインが気になるなら…チェックリスト

「障がいかも?」と感じるきっかけは人それぞれですが、日常生活や人間関係で困りごとが続く場合は、何らかのサインかもしれません。
以下のような特徴が気になる方は、専門機関への相談を検討してみましょう。
- 音や光に過敏で、日常生活に支障が出ることがある
- 人付き合いが極端に苦手で、集団行動や会話が苦痛に感じる
- 物忘れやミスが多く、仕事や学業でトラブルが続く
- こだわりが強く、予定や物の配置が変わると強いストレスを感じる
- 会話や表情から相手の意図を読み取るのが苦手
- 抽象的な思考や計画を立てることが難しい
- 急な予定変更や予想外の出来事に対応できずパニックになる
- 洗浄や確認などの行為を何度も繰り返してしまう
- 言葉の発達が遅い、またはコミュニケーションがうまく取れない
- 学習や金銭管理、時間の理解などが苦手
これらは発達障がい(自閉スペクトラム症・ADHDなど)、知的障がい、精神障がい(強迫性障がい・統合失調症など)…といった精神疾患で見られる傾向があると報告されています。
症状の現れ方や程度は人によって異なりますが、「生きづらさ」を感じる場合は、早めの相談が大切です。
▼▼▼筆者の体験談▼▼▼
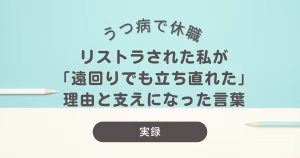
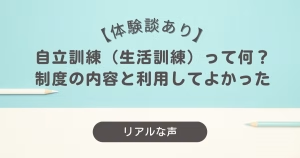
2. まずはどこに相談すればいい?

「気になるサインがあるけど、誰に相談すればいいの?」そんな時は、以下の窓口を活用しましょう。
- 地域の相談支援センター
- 障がいに関する幅広い相談に対応。支援計画や福祉サービスの案内も受けられます。
- 精神科・心療内科
- 診断や医療的なサポートが必要な場合は専門医の受診を検討しましょう。
- 学校や職場の窓口
- 教育現場や職場にも相談員やカウンセラーがいる場合があります。早めに相談することで、配慮や支援を受けやすくなります。
- 保健所・自治体の福祉課
- 地域の福祉サービスや手帳申請、各種サポートの窓口です。
まずは身近な人や信頼できる専門家に相談することが、支援への第一歩です。
相談は匿名でも可能な場合が多く、プライバシーも守られます。
▼▼▼芸能人・有名人の体験談▼▼▼
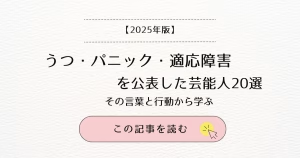
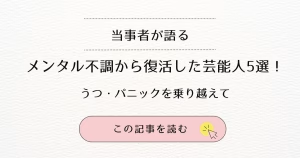
3. 「診断」と「障がい者認定」の違いとは?

障がいのある方への支援には「医師の診断」と「障がい者手帳の取得」という2つのプロセスがあります。
それぞれの違いと流れを知っておきましょう。
- 医師の診断
- 精神科や心療内科、小児科などで専門医が診察し、発達障がいや知的障がい、精神障がいなどの診断を行います。
診断には問診や心理検査、発達歴の聴取などが含まれます。
- 精神科や心療内科、小児科などで専門医が診察し、発達障がいや知的障がい、精神障がいなどの診断を行います。
- 障がい者認定(障がい者手帳の取得)
- 診断結果をもとに、自治体に申請して障がい者手帳(身体・精神・療育)を取得します。
手帳の種類や等級は障がいの内容や程度によって異なります。
- 診断結果をもとに、自治体に申請して障がい者手帳(身体・精神・療育)を取得します。
【手続きの主な流れ】
- 医療機関で診断を受ける
- 必要書類(診断書、写真、申請書など)を準備
- 自治体の福祉課や窓口で申請
- 審査・認定後、障がい者手帳が交付される
診断と手帳取得は別の手続きなので、「診断は受けたけど手帳はまだ」というケースもあります。
手帳があることで受けられる支援が広がるため、必要に応じて取得を検討しましょう。
▼▼▼芸能人・有名人の体験談▼▼▼
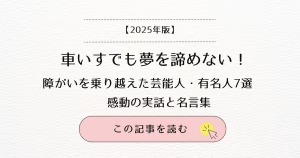
4. 手帳があると何が変わるの?受けられる支援とは

障がい者手帳を取得すると、さまざまな支援やサービスを受けられるようになります。主なメリットを紹介します。
- 障がい者手帳の種類
- 身体障がい者手帳:身体機能に障がいがある場合
- 精神障がい者保健福祉手帳:うつ病や統合失調症など精神障がいの場合
- 療育手帳:知的障がいがある場合
- 受けられる主な支援
- 交通費割引(公共交通機関の割引やタクシー利用補助)
- 就労支援(障がい者雇用枠での就職支援、職場での配慮)
- 障がい年金や各種手当の受給
- 医療費や福祉サービスの助成
- レジャー施設や公共施設の割引
- 生活支援やヘルパー派遣などの福祉サービス

▼▼▼こちらの記事もチェックしてね▼▼▼
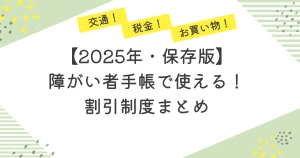
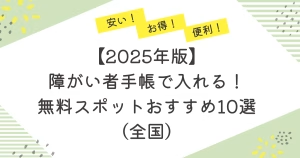
5. 「まだ診断を受けるのが怖い」という方へ
「診断を受けるのが怖い」「障がいと認めるのがつらい」――そんな気持ちを持つのは自然なことです。

しかし、悩みを抱えたままにしておくと、うつや不安障がいなどの二次障がいにつながることもあります。
大切なのは「自分だけじゃない」と知ること、そして一人で抱え込まないことです。
- 同じ悩みを持つ人はたくさんいます。
SNSやコミュニティ、ピアサポートなどで体験談を読むだけでも気持ちが楽になることも。 - 匿名で相談できる窓口もあります。
地域の相談支援センターや電話相談、チャット相談など、気軽に利用できるサービスを活用しましょう。 - 周囲の理解や支援が得られることで、日常生活が大きく変わることもあります。
「困ったら相談する」「無理をしない」――これが、より良い未来への第一歩です。
▼▼▼こちらの記事も参考に▼▼▼
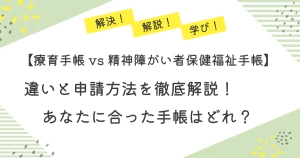
まとめ

障がいのサインに気づいたとき、最初は不安や戸惑いがあって当然です。
しかし、早めに相談し、正しい診断と支援を受けることで、あなた自身や家族の未来は大きく変わります。
この記事が、一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
「障がい者かも…と思ったら最初に読む記事」は、あなたの悩みに寄り添い、診断・相談・支援までの道筋を分かりやすく解説しました。
どんな小さな疑問や不安でも、まずは相談から始めてみてください。
あなたの人生に寄り添うサポートは、きっと見つかります。
この記事が役に立ったと思ったら、ぜひSNSでシェアしてください!😊
▼▼▼筆者の体験談▼▼▼